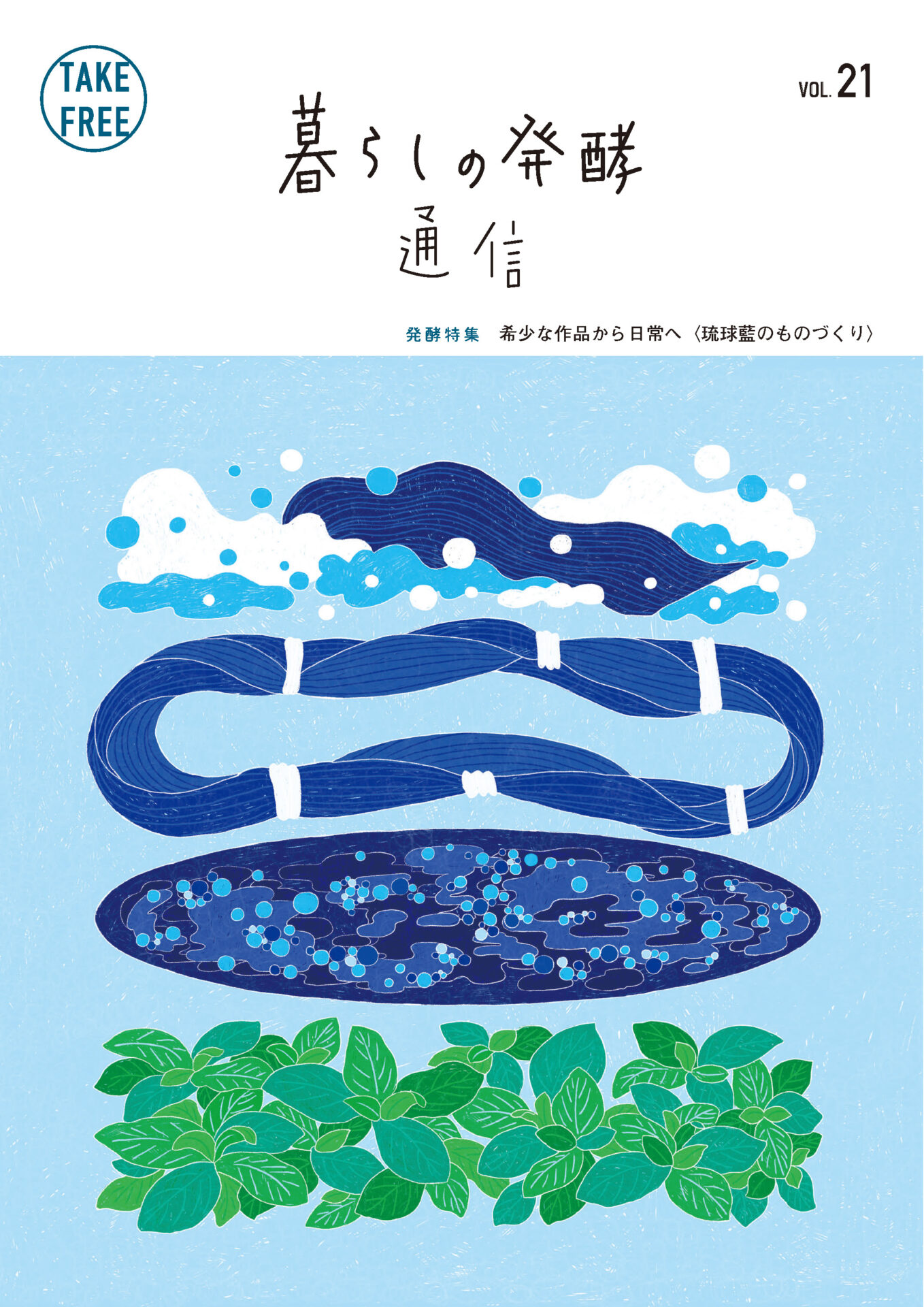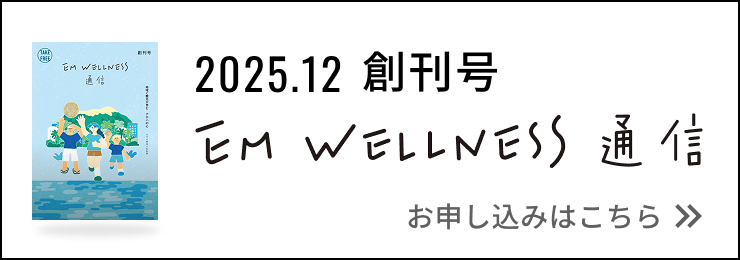地球も文化も「キレイ」を残す

秋田県鹿角市で〈クリーニングえどや〉を営む田中喜昭さんは、洗剤の研究を続けていたところ、皮膚がただれて骨が見えるほど悲惨な状態になる経験をした。現在は石けんなどの自然な洗剤に切り替え、地球と人と地域の“キレイ”を守り続けている。

社長 田中 喜昭さん
秋田県鹿角市で〈クリーニングえどや〉を営む。合成洗剤などの化学物質による自身の体調不良や肌荒れの経験から、石けんやナチュラル素材を使ったクリーニングに切り替えて「水だけで衣類をキレイにする」ことを最終目標とし、日々研究を続けている。
“キレイ”を目指してただれた皮膚
「以前は日本一汚れが取れるクリーニング屋を目指して、合成洗剤の研究をしていました。洗剤の力を発揮させるためには洗う水を軟水にする必要があることに気づき、軟水化させるための薬品を導入しました。洗剤を掛け合わせてより強力に汚れが落ちるものを作り、毎日それを使っていました。そのうち、ある時から薬品を触ると身体に拒否反応が出るようになり、手の指の骨が見えるくらい皮膚がただれてしまったんです。
このまま続けていられないと思った時に、父の代の時はサメの油で作った石けんでクリーニングをしていたことを思い出し、石けんについて調べ始めました。国内で石けんを作っているメーカーを調べて見つけたのが福岡県にあるシャボン玉石けん株式会社でした。

クリーニングで使っているシャボン玉石けんシリーズは店頭で販売もしている。
実は、私はもっと昔にシャボン玉石けんに出逢っていたんですよ。私は子どもの頃からボーイスカウト※に入り、キャンプをして自然の中で過ごすことで自然の大切さなど多くのことを学びました。言ってみればこれが私の環境意識の原点ですね。ボーイスカウトへの恩返しもあって、大人になってからも子ども達の引率兼指導者として活動を続けていました。30年ほど前にボーイスカウトの全国イベントで子どもたちを九州に連れていきました。
その時の会場は牧場で、そこのオーナーから『ここの草は牛に食べさせるものです。牛が洗剤を食べてしまわないように、ここで洗い物をする時は合成洗剤を使わずこの石けんを使ってください』と言われ、粉石けんを渡されました。
でも、私は子ども達にそもそも洗剤すら使わないエコなキャンプを指導していました。食器に袋やラップをかぶせ、その上に食べ物を置き、食べ終えたらそのビニール袋を汚れとともに縛って捨てるという方法です。水が手に入りにくい状況の場合、飲み水の確保が第一優先なので食器を洗う水を必要としない食事の仕方です。
結局、もらった粉石けんは使わずに持ち帰りました。とはいえ、粉石けんをどうやって使ったらいいのかわからず、かといってせっかくいただいたものを捨てることもできずにお店の倉庫で眠らせていました。
※ボーイスカウトとは、少年少女の旺盛な冒険心や好奇心をキャンプ生活や自然観察、グループでのゲームなどの中で発揮させ、「遊び」を通して自立心や協調性、リーダーシップを身につけさせる世界的運動。
眠らせていた石けんが宝物だった
クリーニングに石けんを使おうと思った時にこの石けんのことを思い出し、倉庫から引っ張り出してみたら、〈シャボン玉石けん〉と書いてあるじゃないですか!さっそく使ってみると、汚れ落ちはいいし手荒れもしないので『これはいい!』と思い、すぐに福岡県に飛びましたね。

クリーニングえどやの店内はクリーニング店特有の化学的なニオイがなく、石けんの爽やかな香りがする。
シャボン玉石けんの本社にアポイントを取らずに行って、受付で『社長に会いたい』と懇願したら、なんとその時はタイミング良くお会いできたんです。合成洗剤の影響で身体が大変になった自分の経験をシャボン玉石けんの(前)社長にお話ししたら、『私もあなたと同じ経験をしました。だから合成洗剤から石けんに切り替えたんです』という話を聞かせてくださいました。どこの誰かもわからないような自分が急に訪ねてきたのに受け入れてくださった嬉しさと、同じ境遇のお話に涙がボロボロとこぼれました。」
タピオカ粉で服にコーティング?!
現在、田中さんのお店〈クリーニングえどや〉では石けんを中心に、その他の天然素材やEM(有用微生物群)を活用してクリーニングを行っている。
「環境問題や自然由来の素材を使った洗剤に関心が向いた時にEMのことを知りました。クリーニング屋としてEMを研究した結果、石けんとEMをある一定比率にした時に石けんの効果が引き出されることと、仕上げに使う糊剤とEMを一緒に使うとすごく良いことがわかりました。うちではワイシャツなどをパリッとさせるための糊剤にタピオカ粉を使っています。タピオカ粉のでんぷん質が糊の役割になるんですよ。タピオカ粉にEMを合わせることで糊剤の伸びが良くなり、着た後に洗濯をする時の糊離れも良くなります。
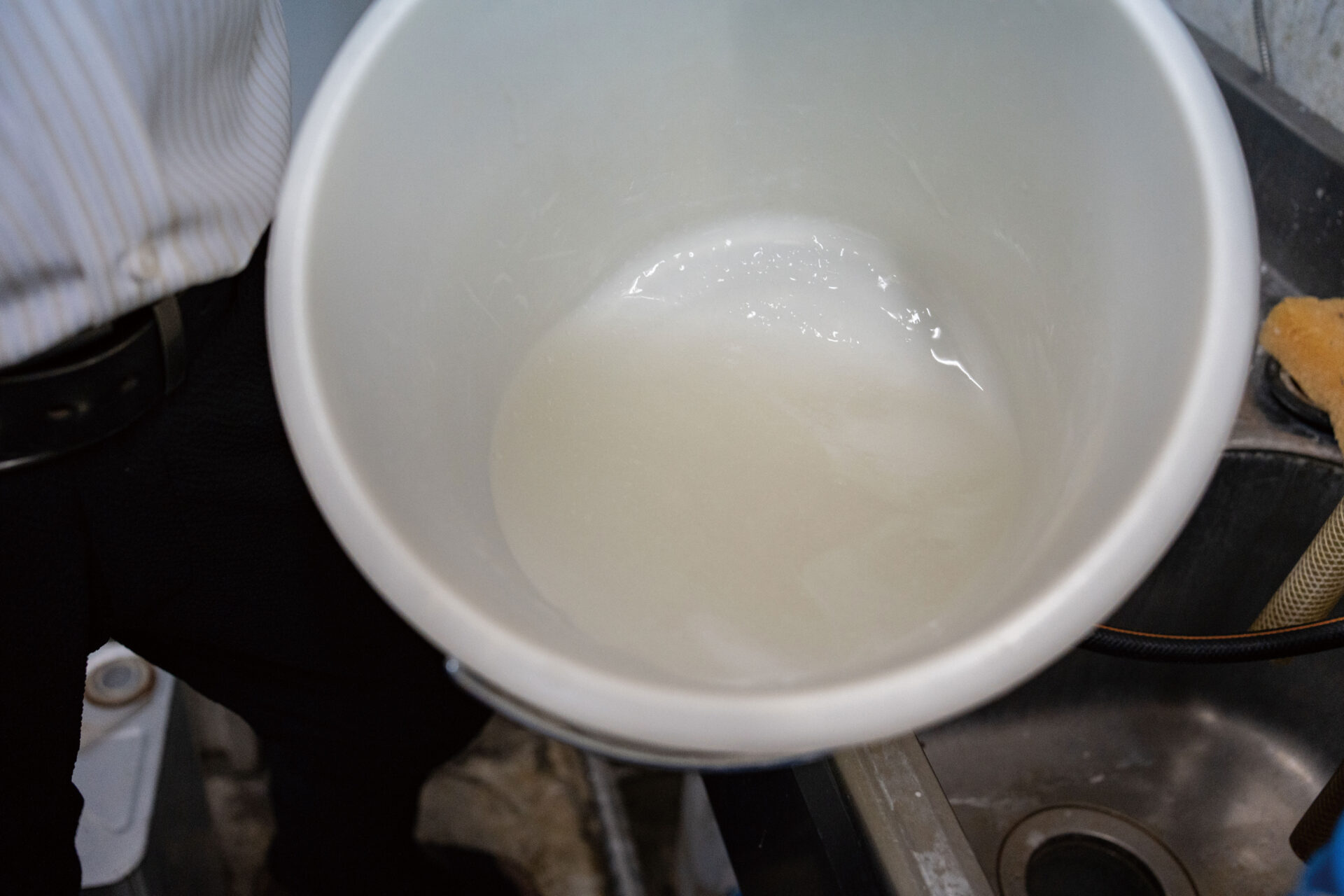
タピオカ粉は元々食品なので、肌に触れてももちろん安全。
私が目指しているクリーニングは、衣類にも着る人にも地球にも、そしてクリーニング屋で働く自分たちにも負荷が少ない、ローインパクトクリーニングです。ボーイスカウトでは洗剤を使わないキャンプを実践していましたが、食器を洗う必要がないから、食器は傷まずに長持ちします。
クリーニングもまさにそのイメージで、服が汚れないようにコーティングできれば服が長持ちします。タピオカ粉は糊剤としてだけではなく、そうしたコーティングの役割も担っているんです。汚れはコーティングしているタピオカ粉の方につくので、汚れが付いたタピオカ粉を取れば服はキレイなわけです。

一般的なクリーニングで使う糊剤は木工用ボンドと同じ成分なので、一度ついたらなかなか取れません。衣類の上に糊剤を塗ってその上に汚れがついて、またさらに糊剤をのせていくので、汚れがミルフィーユ状になり黒ずんでいきます。でも、タピオカ粉とEMの糊剤は洗濯で100%落ちます。洗剤も糊も天然成分なので、『うちのワイシャツは食べられますよ』なんてお伝えしています(笑)。」
地域の文化も“キレイ”に残す
鹿角市は青森県と岩手県の県境に位置する山間地域。人口3万人にも満たない小さな市だが、国重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産に登録されている花輪ばやしや毛馬内盆踊り、世界遺産に登録されている縄文遺跡群〈大湯環状列石〉など歴史と文化に富んでいる。

「この地域は夏に祭がたくさんあって、浴衣を着る機会が多く、うちのクリーニング屋でも毎年何百枚もの浴衣を洗っています。集落ごとに柄が異なり、集落の仲間の結婚式には浴衣を正装とするぐらい浴衣を着る文化が大切にされています。私がクリーニング屋を家業として続けている理由の一つに、そうした地域の祭りや浴衣の文化を守って盛り上げていきたいという想いがあります。」

また、鹿角市には奈良時代から伝承されてきた〈鹿角紫根染・茜染〉という草木染があるが、明治期に一度途絶えてしまった。最初に復活させたのは先代まで紫根染めを家業としていた栗山文次郎氏(後の人間国宝)。その技術は息子の文一郎氏に引き継がれたが、継承者がおらず再度途絶えてしまった。再び復活させたのは元教員の關(せき)幸子さん。

元小学校教諭を務めていた關さんは、社会見学で児童を連れて行った際に初めて鹿角紫根染・茜染に出逢った。
關さんは栗山家に伝わって来た伝統技法を継承しつつ、染め体験などを通して鹿角紫根染・茜染の普及活動を行っている。関さんは「地域の宝である紫根染・茜染を多くの方にみてもらいたい」と、鹿角市の事業として地元の商店街アーケードに75枚の紫根染・茜染タペストリーを飾るイベントを実施。

その時に、地域活動を精力的にされていた田中さんが企画から運営までを全面的に協力した。関さんは「田中さんから『イベントで展示した作品はすべてうちが責任を持って洗います』と心強い言葉をいただけて、本当にお世話になりました。田中さんの奥様含め、地域の方々に栗山家の着物を着て演舞していただきました」と当時の様子を振り返る。

「神の坐す布」と称された、鹿角紫根染・茜染。古代技法で作られたものは50年以上経った今でも輝き続けている。
「着る」とその先にある「洗う」。それは「着る」ことで伝統文化を継承し、地球と人にやさしい「洗う」ことを通じて、人と人がつながっていく。「洗う」とは目の前から汚れが無くなることだけではなく、人や地域・文化とのつながりをも生みだすものであると田中さんは教えてくれた。
2024年9月取材